○湯沢市水道事業等給水工事の施工等に関する基準
平成17年3月22日
水道事業訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、湯沢市水道事業等給水条例(平成17年湯沢市条例第225号)並びに湯沢市水道事業等給水条例施行規則(平成17年湯沢市規則第161号)に定めるものを除くほか、給水工事の施工の基準及び検査等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申込みの手続)
第2条 湯沢市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)は、給水工事を施工しようとする場合は、給水工事台帳に所要事項を記入し、必要な設計図を添付して給水工事を申込み、あらかじめ上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けるものとする。
(設計変更)
第3条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに設計変更の手続をしなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 栓数の増減及び口径に変更があったとき。
(2) 分岐点に変更があったとき。
(3) 給水管の延長又は位置に変更があったとき。
(4) 管種及び管径に変更があったとき。
(給水方式)
第4条 給水管の管径及び水圧が使用水量に対して十分な場合は、直結直圧式給水とする。ただし、管理者が認める場合の他、特に水圧を必要とする箇所又は一時に多量の水を使用する箇所及び4階以上の建物に給水するときは受水槽式給水によらなければならない。
2 受水槽式による給水の場合は、受水槽の容量を計画1日使用水量の10分の4から10分の6以上のものとしなければならない。
(管種)
第5条 給水管は、構造材質基準の性能基準に適合していなければならない。また、施行にあたっては、構造材質基準の給水装置システム基準に適合するとともに、布設場所の地質、管の受ける外力、気候、管の特性、通水後の維持管理などを考慮し、もっとも適切な管種を選定する。
(管の連結)
第6条 給水管は、市の水道以外の水道、井戸水及び排水等の管並びに施設と直接連結してはならない。
(配管)
第7条 給水管の布設位置は、やむを得ない場合のほか、下水、便所及び汚水タンク等の場所を避けるとともに、止水栓、メーター等の設置を十分考慮し、維持管理に支障をきたさないよう配管しなければならない。
2 給水装置の位置の変更、改造及び廃止工事等において給水管を切断する場合は、原則として配水管との分岐点で切断しなければならない。
(水槽等への給水)
第8条 水槽、プール、噴水その他水を入れ、又は受ける器具及び施設への給水に際しては、次による方法で施工しなければならない。
(1) 逆流を阻止するため落し込みとし、落し口と、満水面との間隔は、管の管径以上(最小50ミリメートル)とする。
(2) 原則として越流装置を設けるものとし、水を汚染したり、又は漏水するような構造であってはならない。
(排気、排水装置)
第9条 給水管中に停滞空気が生じて通水を阻害し、又は死水が停滞するおそれのあるところには、それぞれ排気装置又は排水装置を設ける等、適切な措置を講じなければならない。
(器具の連結)
第10条 配水管の水圧低下又は断水等によって生ずる真空作用による逆流を防止するため、原則として器具に有効な逆流防止装置を設けなければならない。
2 給水装置には、ポンプを直接連結してはならない。
(水道メーター)
第11条 水道メーターは、検定期限内のものであって原則として使用水量に適したものを給水栓より低位に設置しなければならない。
2 水道メーターは、給水管分岐部に最も近接した敷地部分とし、検針及び取替作業等が容易な場所で、かつ、汚水や雨水が流入したり、障害物の置かれやすい場所を避けて設置しなければならない。
3 水道メーターは、すべて取り付ける前に管内の異物を取り除き、メーターの矢印を流水方向として水平に取り付けること。
(配水管からの分岐)
第12条 配水管からの分岐は、次によらなければならない。
(1) 分水栓を取り付ける場合は、各分水栓、異型管との間隔を30センチメートル以上離すこと。
(2) 口径50ミリメートル以上の分水栓を取り付ける場合は、割T字管又はT字管を使用すること。
(止水栓、制水弁)
第13条 単独引込みの場合において、止水栓は公私境界線ぎわの宅地内とし、制水弁の取付位置は分岐箇所に取り付けること。
2 遠距離の場合は、2箇所以上に取り付けるものとし、同一給水管から2戸以上に分岐する場合は、前項の規定により取り付けるほか、各戸の分岐点と水道メーターの間にそれぞれ取り付けるものとする。
3 既設の装置から分岐するときは、前項の規定に準じて取り付けるものとする。
4 支栓の多い給水装置などには修理の利便を図るためバルブ等を取り付けるものとする。
5 機械その他特殊な器具の設置箇所の手前にはバルブ等を取付け、かつ、有効な逆流阻止装置を設けなければならない。
6 水道メーター筐内に逆流防止のための逆流防止弁を取り付けなければならない。
(不凍装置)
第14条 給水管の凍結を防止するために、不凍給水栓又は不凍止水栓を設置しなければならない。
2 不凍止水栓は、給水栓数を考慮した本数を取り付けるものとする。
3 不凍止水栓の位置は屋内とし、排水を良くするため周囲に砂利をつめ、かつ、修理しやすいように取り付けるものとする。
(きょうの取付け)
第15条 水道メーター、止水栓及び制水弁等は、きょうに入れて保護し、それぞれの器具が中心になるように取り付けるものとする。
(せん孔)
第16条 せん孔は、配水管に対して垂直に行わなければならない。
2 鋳鉄管のせん孔は防蝕用のコアーを挿入し、ビニール管のせん孔については管を損傷し、又は屑が通水を阻害することのないよう特に注意しなければならない。
(保護工)
第17条 給水管の保護については、次の各項によらなければならない。
2 侵食のおそれがある場合は、侵食防止上適切な措置を講ずるものとする。
3 軌道下を横断する場合は、関係機関の指示を受けて適切に施行する。
4 各種地下埋設物に近接して配管する場合は、所管の係に連絡し、適切な指示を受けて施行する。
5 蛇口取付けの屋外立上り管は、原則として不凍給水栓とする。ただし、当該栓に不凍止水栓を取り付ける場合はこの限りでない。
6 管の末端、曲部その他で接合部離脱のおそれがある箇所には防護を施すものとする。
7 側溝等の横断については、所管の係と協議し、適切な指示を受けて施行する。
(埋戻し)
第18条 埋戻しに際しては、管肌に傷を与えないように石塊、コンクリートその他の雑物をよく取除いた下層土又は砂をもって管を丁寧に包み、以下各層ごとによくつき固め、地面におうとつを生じないようにしなければならない。
2 水圧検査を受ける場合の埋もどしには、原則として継手部分を露出させておくものとする。
(排気、洗浄)
第19条 工事完了の場合は、管の排気と洗浄を徐々に、かつ、十分に行わなければならない。
(埋設深度)
第20条 各種管の埋設深度及び掘削幅は、埋設深度及び掘削幅標準表(別表第2)による。ただし、道路管理者の許可が得られる場合は、浅層埋設とすることができる。
(施工)
第21条 各種管の接合については、日本水道協会(水道施設設計指針)に基づいて行う。
(竣工届)
第22条 指定工事事業者は、工事が竣工したときは、遅滞なく竣工届に竣工図(管理者が第2条第2項ただし書の規定により略図を認めた場合は精算略図(以下同じ。))を添えて提出し、工事検査を受けなければならない。
(検査の方法)
第23条 検査は、設計図と対照して給水装置の凍結防止装置、布設延長、埋設深度及び耐圧等について重点的に実施するものとする。
第24条 指定工事事業者は、検査当日あらかじめ前条の規定による検査に必要な準備をしておかなければならない。
2 検査員は、前項の箇所以外についても必要と認めたときは指定工事事業者に掘り起させることができる。
第25条 検査員は、給水装置の各部の漏水の有無を検査するため、ポリ管、鋼管及びビニール管については、1.75メガパスカル(1分間)、ゴム輪型ビニール管、鋳鉄管については、1.0メガパスカル(30分間)の水圧をかけ検査を行うものとする。
(材料の規格)
第26条 材料は、日本水道協会(認証登録リスト)に登録された規格品のものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市水道事業給水工事の施工等に関する基準(平成6年6月28日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日上下水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
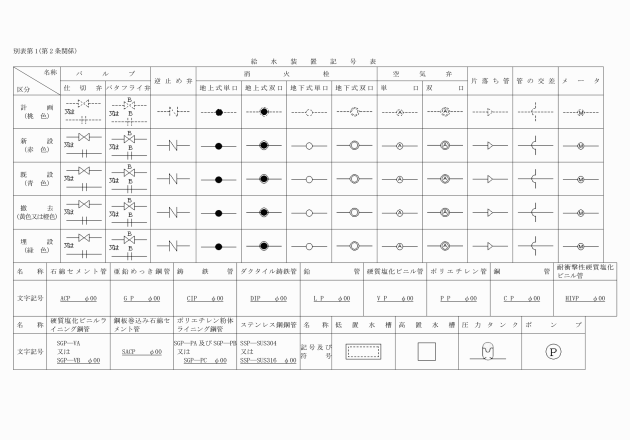
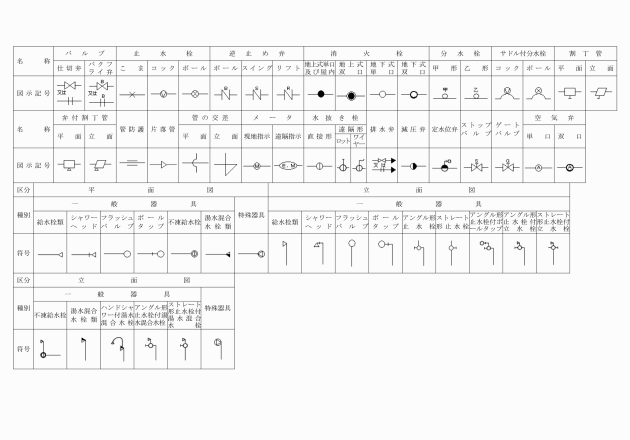
別表第2(第20条関係)
埋設深度及び掘削幅標準表
区分 | 埋設深度(φ13~φ50) | 掘削幅員 | 埋設深度(φ75以上) | 掘削幅員 |
公道 | 120cm以上 | 60cm | 120cm以上 | 60cm |
公道に準ずる私道 | 120cm以上 | 60cm | 120cm以上 | 60cm |
歩道 | 90cm以上 | 60cm | 120cm以上 | 60cm |
私道 | 60cm以上 | 40cm | 120cm以上 | 60cm |
宅地 | 45cm以上 | 40cm | 120cm以上 | 60cm |
公道小穴堀(φ50~φ150) | 120cm以上 | 100cm |
|
|
φ200以上 | 120cm以上 | 120cm |
|
|